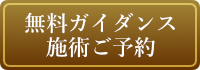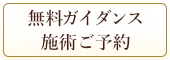- ホーム
- ブログ
- ―鍼灸師・鍼灸学生向け講座について
- 鍼灸師学生コースで学ぶことでどんなことが活かされる① 坂本指圧マッサージ術流の前揉法後揉法のポイント
鍼灸師学生コースで学ぶことでどんなことが活かされる① 坂本指圧マッサージ術流の前揉法後揉法のポイント
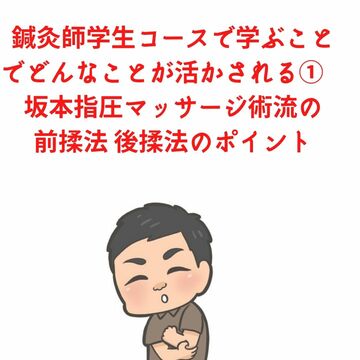
こんにちは
坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です
鍼灸師学生コースがある3つ理由
についてお話してます
- 坂本指圧マッサージ術は鍼灸と柔整の考えが元である(先鋭化と鍼尖転移術が原点について)
- 鍼灸師学生コースでどんな形の講義になる(なじみ深い経絡経穴の考え方を元に展開する)
- 鍼灸師学生コースで学ぶことでどんなことが活かされる
前回3回にわたり
- 坂本指圧マッサージ術は鍼灸と柔整の考えが元である(先鋭化と鍼尖転移術が原点について)
- 鍼灸師学生コースでどんな形の講義になる(なじみ深い経絡経穴の考え方を元に展開する)
についてお話ししました。
前回3回までのブログはこちらをご覧ください
1についてはこちら
2についてはこちら
をご参照ください
今回の内容は
鍼灸師学生コースがある3つ理由の3つめ
3鍼灸師学生コースで学ぶことでどんな事に活かされる(指圧マッサージ術が鍼灸分野で応用できる事とは)
指圧マッサージ術が鍼灸分野で応用できることとは3つ
- より効果の高い前揉法、後揉法に活かせる
- 鍼灸師の命である指を傷めずにお施術す事ができる
- セルフケア指圧の指導の仕方がわかる(施術の一例紹介)
の3点です
今回はこの1より効果の高い前揉法、後揉法に活かせるについてお話しいてきます それではいってみましょう1より効果の高い前揉法、後揉法に活かせる
前揉法は刺す前に行う手技で鍼を刺すにあたって、できるだけ刺入時の違和感を軽減させる為に行い
後揉法は鍼を抜いた後に刺入時の痛みの余韻、違和感を軽減させる事が主な目的ですここでは指圧マッサージを学ぶことで前揉法、後揉法にどう活かせるのかをご説明します
さて前揉法、後揉法の手技方法役割ですがですが
鍼灸師 鍼灸を志す学生の皆さんならお分かりのことでしょう
前揉法・後揉法の役割考えは教わるがその詳しい施術方法役割は教わっていない事を
①前揉法・後揉法の役割考は教わるがその詳しい施術方法は教わっていないのが現実
それはなぜか?
(私も鍼灸科の教員として経験したことですが)
それは鍼灸学校は前揉・後揉その揉捏法の仕方を鍼灸師の先生も詳しく習ってないからです(鍼灸のぷrpであっても手技のプロではないから)
これは大きな盲点です(学校によっては詳しく習っている所があるかもしてませんが大半は詳しくはしていないでしょう)
非常に前揉法・後揉法は大切なのです
ここではどのように大切ななんかをそれぞれお話していきたいと思います
私も鍼灸科の教員として経験から指圧マッサージ塾を開いた際には
鍼灸師鍼灸学生の皆さんに効果の得られる前揉法後揉法をお話したいと思ったのが
鍼灸コースを開いた理由の一つなんです
前揉法と指圧マッサージによる応用法
②前揉法の大切な役割(凝りや緊張は筋肉だけでなく皮膚にも起こる)
人は常に外敵からいつでも身を守れるよう、筋肉を働きやすくまたは守るために固くなります
これは皮膚も同じです 皮膚も固く緊張しなるのです
この緊張状態が続くと、痛みの閾値は低くなり感じやすくなります
そうなるとさらに体は危険と感じ緊張は増し皮膚も筋も固く交感神経(緊張させる神経)も更に高まります

だから体には緊張しなくていいよ 外敵ではないよと 安心させて(痛みの閾値を上げなくて)あげなくてはなりません
その為にはどうすればよいか
体に触れ 少しずづ刺激を加えていく体に慣れ馴染ます動作を行うのです
これこそが前揉法の大切な事です 前揉法の前提は痛みや違和感を押さえる事ですが
その痛みや違和感を引き起こす原因をり除くことにあるのです
それが刺激に慣れさせることです
その方法が
体には緊張しなくていいよ 外敵ではないよと 安心させて
体に触れ 少しずづ刺激を加えていく体に慣れ馴染ます動作を行う事です

③前揉法の具体的な施術法(坂本指圧マッサージ術流の刺鍼前の前揉法)
前揉法とは軽い揉捏法というイメージが多いでしょうが
私は軽く摩る軽擦法から少し強めの軽擦法やそして揉捏法としていきます
そして施術部位も
交感神経が高まり緊張が増しやすい背中首腰を避けまずは手足→腕下腿→太もも上腕→肩臀部→
体幹に来るように行い
最後に鍼を行う部位に対して行います重点的に行います(この場所に行うのみを前揉法といわれまずが私は違うと考えます)
大切な事は手足に意識を向け鍼を受け入れやすいようリラックスさせることが大切です
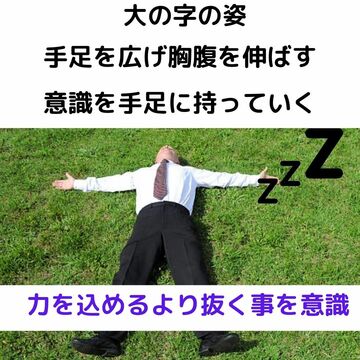
手足末端から施術していく方法は私の基本施術は仰向け施術でも詳しくお話しいていますのでよければご覧ください
大切な事は体全身の緊張をとり体を安心させて ここ打つよ~体に教えてあげるように最初は軽く(軽擦→揉捏)か
ら施術し体になじましていくことが大切なんです(^^♪
ちなみに
当塾 治療院で鍼を打つときは基本的に
指圧マッサージ施術を行い十分緊張をとって(全身の緊張をとる)から刺鍼部位に軽い揉捏法を加えながら刺鍼しています
治療院では基本指圧マッサージで施術を行い それでも取りきらないとき また自律神経の超調節のため
指圧マッサージ施術後に鍼術を行う事があります
治療院のメニューに関してはこちらをご覧ください
後揉法と指圧マッサージによる応用法
④後揉法の役割
後揉法の主な役割は鍼を抜いた後の違和感の軽減の為に行われるのですがそれだけではありません
より鍼の効果を高める働くがあり、また逆に抜鍼後に好転反応一つである脳貧血を押さえる作用がある
まずここでは
- 抜鍼後の違和感痛みの軽減
- 鍼の効果を高める
- 抜鍼後に好転反応一つである脳貧血を押さえる作用など(過剰好転の軽減緩和)
について簡単にお話します
1抜鍼後の違和感痛みの軽減
痛みがある後 無意識にその場所を押さえたり揉むと痛みが治まります それはなぜでしょう?
これは痛みを伝える神経と押さえたり揉んだりする神経が違い
痛みの神経は細く 押したり揉んだりする神経は太い構造をしており
神経の性質上 細神経(痛みの神経)の後に太い神経(押したり揉んだりする)の情報が入ると
2鍼の効果を高めるこができる
太い神経(押したり揉んだり)が細い神経(痛み)の情報を遮断する性質があるのです
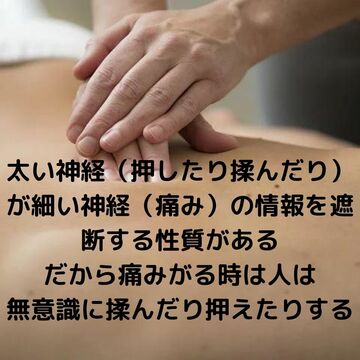
これが痛みのある時に揉むと痛みが治まる理由です
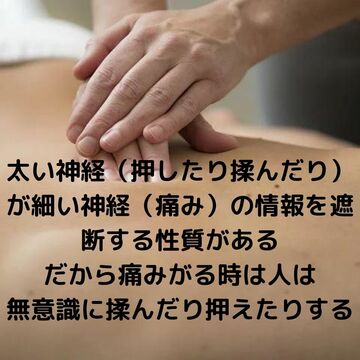
これが後揉法の一番の役割ですな
2鍼の効果を高めるこができる
鍼はツボや刺鍼ポイントに対し刺激を行い その効果は全身に広がります
その効果より高めていくことができます
しかし注意すべきはその刺激量です 過剰にしすぎると好転反応が強く出てしまうので
好転反応を逆に押さえるために後揉法(揉捏法)の後 軽い軽擦で全身を施術していきます(仕上げの後揉法)
3抜鍼後に好転反応一つである脳貧血を押さえる作用など(過剰好反応転の軽減緩和)
よく見かけると思いますが
施術終了前に背中などを叩いたり(叩打法) 撫でたり(軽擦)には意味があるのです
それが過剰好転反応緩和です

施術を受けている間は体にいろいろな反応(血の巡りの改善 ホルモン神経の生体反応)が起こます
また 施術後もその作用は更に進み より施術効果を高めていくことになります
(そのため施術後 効果が一現れるのが数時間から数日かかるのがその為)
しかしそれに伴い 過剰な反応が起こる事があります それが好転反応
特に施術終了時は副交感神経が更新して血圧が低下している事が多いです その為急に起き上がると
血圧が上昇しにくく脳貧血になる事があるのです(起立性低血圧)
過剰な好転反応を抑えるために
- 施術後は休憩していたてからお帰りいただく
- 施術後 当日の飲酒 お風呂を控える
- 早めに就寝する
- 施術後は過剰な仕事運動は控える
などの注意事項があるのはその為なんです
好転反応 その時の体調 環境 施術の刺激量によっても変化しますができるだけ
過剰におこる過剰好転反応の予防するのが大切です
その為にも後揉法は大切です
⑤後揉法の施術法
まずは施術部位に対して後揉法(揉捏法)を行います
その後、その他の
抜鍼動作とその後施術部位にたいする後揉法(揉捏法)を行った後
全身に対し軽擦法を行います
これは上記で述べた
脳貧血などの好転反応を緩和させる作用であり
施術終了後 少しづつ覚醒して血の巡りをよくしていくことにあるのです。
鍼の効果が本当に出てくるのは基本 施術後 数時間~数日たってからです
それは鍼により刺激を受けた体は
軽い動作で血がめぐりやすくなり
休憩する(睡眠する事で)更にほぐれやすくなるからです。
その過程で逆に過剰な好反応が出やすくなるのでその予防のためにも後揉法は必要なんです
(指圧マッサージもほぼ同じ過程です)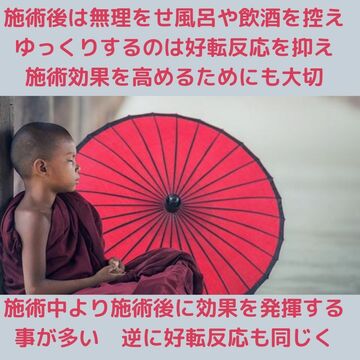
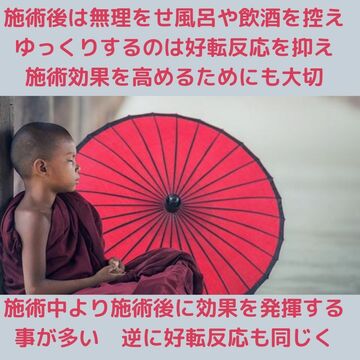
このように前揉法・後揉法それぞれに大切な役割があります
前揉法・後揉法を考えて行うか行わないかだけでも施術効果だけでなくリスク管理に大きくつながるのです
鍼灸コースではこのとり友好的な前揉法・後揉法についてもお話していきます(^^♪
今回もありがとうございました
関連エントリー
-
 より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング
こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご
より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング
こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご
-
 肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)
こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー
肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)
こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー
-
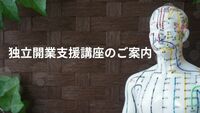 坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!
「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は
坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!
「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は
-
 10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ
毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ
10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ
毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ
-
 足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)
指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧
足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)
指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧


 指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら
指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら